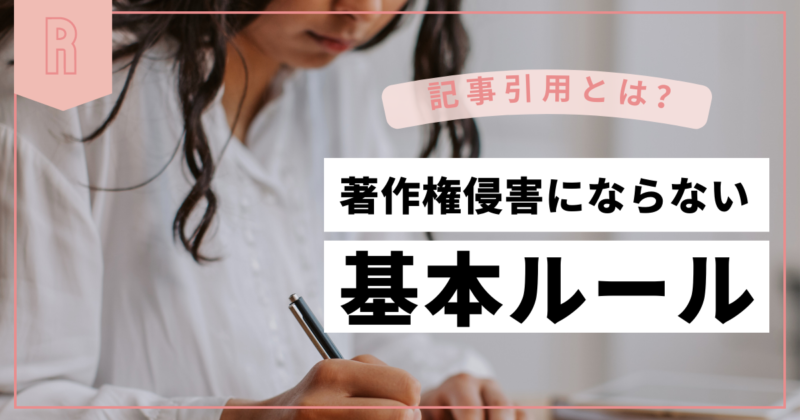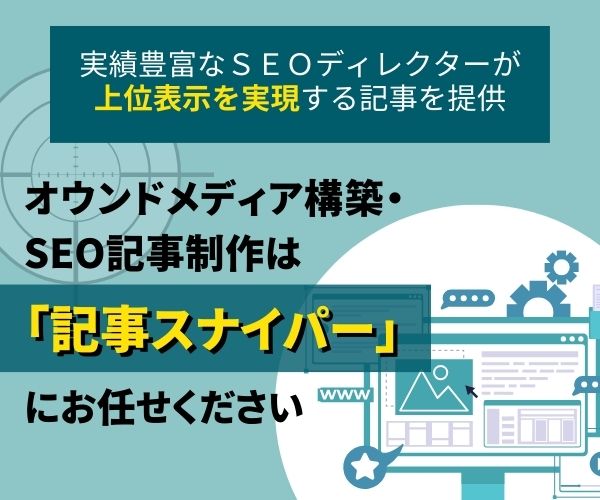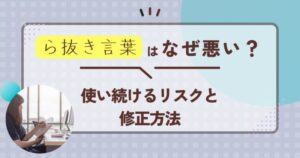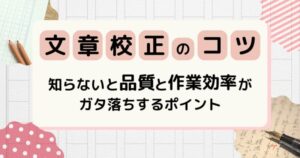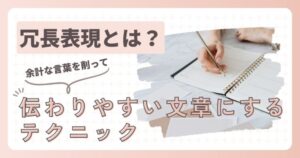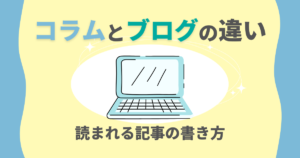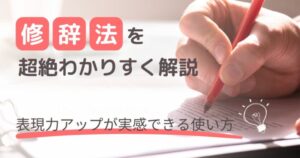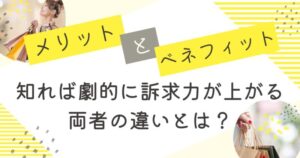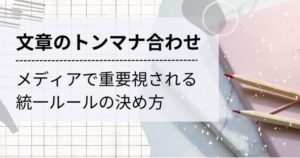文章を書く機会があれば、一度は必ず「引用」で悩んだことがあるのではないでしょうか。
文章を書く際に「引用」の方法は重要となるにもかかわらず、多くの人が理解しているとは言い難いのが現状です。
そこでこの記事では、引用の基礎知識を一から丁寧に解説していきます。引用の仕方の基本を押さえておけば、自分の文章の説得力や信頼度が向上するでしょう。
記事の引用とは?
最初に、記事の引用とは何かを説明します。引用と同じような意味を持つ類義語との比較を通じて、それぞれの言葉にどのような違いがあるのかを理解しましょう。
引用と類似語の意味の違い
引用とは、他人の著作物、たとえば文章や画像などをそのまま自分の文章の中で使用することを言います。この際、引用元の内容は変更せず、自分の文章の内容を補完または裏付ける形で使用するのが原則です。
引用では、主体となるのは自分の文章であり、引用される情報はその文章を補強するためのエビデンスとして使われることになります。
引用する際には、読者が原文と自分の文章とを区別できるようにすることが必須です。引用箇所は通常、引用記号で囲われ、引用元(出典)を示す注釈が付きます。
引用と似た言葉が「転載」です。転載も他人の著作物をそのまま自分の文章の中で使用する行為を指しますが、この場合、主体は他人の著作物となります。
つまり、転載は他人の著作物を中心に据え、その内容をそのまま伝えることに重きを置いた書き方となります。そのため、転載には基本的に著作者の許諾が必要です。
また「参考」という言葉は、他人の著作物や書籍、雑誌、または人の意見などから得た情報を自分の文章の中で要約し、使用することを指すのが一般的です。
ただし、参考は情報の全てを直接引用するわけではなく、その内容を参考にして自分なりに解釈や要約を行います。
「参照」という言葉は、他人の著作物の情報を要約し自分の文章で使用する行為を言うため「参考」に非常に近い概念ですが、対象となるのは具体的な書籍や雑誌など、形として存在する著作物が中心です。
「出典」という言葉は、情報の出所を示すために使用されます。引用や参照の際に、その情報がどこから来たのかを明記することで、読者が必要な場合に原典を参照できるようにするため、また情報の信憑性を保証するために必要な行為です。
出典は、引用や参照した情報の信頼性を保証し、読者が原典を探しやすくするために必要で、フッターノート、エンドノート、参考文献リストなど、さまざまな形で表記されます。
以上が「引用」「転載」「参考」「参照」「出典」のそれぞれの概念と違いです。これらを理解し適切に使用することで、自分の文章や議論に深みと信頼性をもたらすことができるでしょう。
WEB記事における引用
WEB記事を執筆する際にも「引用」は必要であり重要です。以下の観点から、WEB記事でも引用しなければなりません。
情報の正確性と信憑性
他人の著作物や研究から得た情報を使用する際、引用することでその情報の正確性と信憑性を保証します。引用により読者は、執筆の際に情報をどこから得たのか、それがどの程度信頼できる情報なのかを判断することが可能です。
著作権の尊重
他人の著作物をそのまま使用する場合、引用は著作権法により保護されています。しかし、引用する際には引用元を明示することが必要です。また、引用する範囲にも一定の制限があります。
プラジャリズム(盗用)の防止
他人の著作物や考えを自分のものとして提示することは、学問的または倫理的に許容されません。引用を正しく行うことで、自分の作品が他人の作品に基づいていることを明示し、プラジャリズムを避けることができます。
したがって、WEB上で記事を執筆する際も、他人の言葉や考えを使用する場合は適切に引用し、引用元を明示することが必須です。
また、WEB上での引用の際には、可能であれば引用元へのリンクを提供することが推奨されます。これにより、読者は直接引用元を確認し、情報の正確性を確認することが容易になります。
記事を引用するときの条件
記事を引用する場合には、次のポイントに気をつけてください。引用にはルールがあるので、そのルールを明確に理解しておくことが大切です。
引用する必然性がある
引用は他人の著作物を自分の作品に取り入れる重要なツールですが、無闇に使用すべきではありません。
引用する必然性がある場合、つまりその情報が作品の議論を補強し、読者に対して追加的な価値を提供する場合のみ使用すべきです。
引用する情報が作品の主張を明確に裏付ける、または論点に深みや洞察を追加するときのみ引用を行いましょう。
引用箇所と自分の著作物が区別されている
引用した内容は、引用元の著作物とあなた自身の作品がはっきりと区別できるように表現する必要があります。
これは、読者が引用箇所とあなた自身の文章を明確に識別できるようにするためです。
引用部分は通常、引用記号やインデント(字下げ)等で明確に区別され、引用元の情報とあなたの独自の考察が混同されないようにする必要があります。
自分の著作物が主体である
引用は作品の一部であり、自身の議論を補強するためのものです。そのため、自分の著作物が主体であり、引用箇所が全体の一部とならなければなりません。
引用箇所が文章全体を占めるような状態になると、著作権侵害やプラジャリズムの問題が生じる可能性があります。
引用箇所はあくまで補足であり、オリジナルの議論や意見を補強するためのものと考えてください。
出典が明らかになっている
引用を行う際には、出典を明記することが必須です。引用元の情報は、引用した作品のタイトル、著者名、出版日、ページ番号など、読者が原典を特定し、必要に応じて直接参照できるようにするために記載します。
この出典明示は、引用内容の信憑性を保証し、著作権法に基づく義務を遵守するための重要なプロセスです。
引用のときの著作物の種類別の表記方法
文章に限らず、画像やSNSの投稿、新聞記事なども適切に引用しなければなりません。
以下では、それぞれの著作物の具体的な引用方法について解説していきます。
文章
文章の引用の際には、引用部分をダブルクォート(” “)やインデントで明確に区別し、その直後に出典を記述します。
例えば、「”引用部分”(出典)」と表記するとよいでしょう。また、APAスタイルなどの特定の引用スタイルに従う場合は、そのルールで記述します。
画像
画像の引用の際には、画像の直下やキャプション内に出典を明記します。出典を明記する際には、著作権者の名前や作品名、ライセンス情報(CC BYなど)を含めるとよいでしょう。
例:「出典:[著作権者名] / [作品名] / [ライセンス]」
以下の記事では、著作権の基本とスクショが違法行為にならないように守るべきポイントを解説しています。
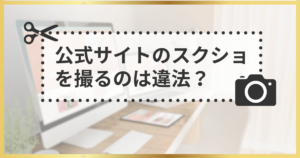
SNSの投稿
SNSの投稿を引用する際は、該当SNSの埋め込み機能を利用することが一般的です。これにより、投稿者の名前や投稿の日時などの詳細情報が自動的に表示されます。
ただし、これが不可能な場合や望ましくない場合は、引用部分を明確に区別し、その出典を明記しましょう。
書籍・雑誌
書籍や雑誌を引用する際には、作者の名前、書籍名、発行年、発行者名、ページ番号などの情報を記載します。
例えば、「(作者名、発行年、 “書籍名”、 発行者名、 p.ページ番号)」という形で表記するとよいでしょう。
新聞記事
新聞記事を引用する場合、記事のタイトル、新聞名、発行日、場合によっては記者名を明記しましょう。
例:「”記事タイトル”、新聞名、発行日」
また、オンラインで公開されている場合は、公開日やアクセス日も加えるとより詳細な引用となります。
記事を引用するときの注意点
記事を引用する場合には、以下のポイントに特に注意してください。引用を表記しようとする方が特に間違いやすいポイントです。
原則オリジナルのソースから引用する
信頼性と精度を確保するために、原則として情報のオリジナルのソースから引用することが重要です。
セカンダリーソース(つまり、元の情報を解釈または要約した情報)から引用すると、情報が歪んだり誤解が生じたりする可能性があるでしょう。
また、オリジナルのソースから引用することにより、読者に対して情報の信頼性を保証し、自身の説明や解釈が元の情報に忠実であることを証明します。
勝手に改変しない
引用を行う際には、元の文言を勝手に改変してはなりません。引用する内容は原則として、原文の意味を忠実に保持する形で使用するべきです。
改変や書き換えが必要な場合でも、それが引用元の内容を歪めるものであってはならず、原文の意味を変えてしまうような改変は避けなければなりません。
引用は他人の考えや意見を正確に伝えることが目的であり、その精神を尊重することが求められます。
注意したい著作権侵害になるパターン
以下のようなケースでは、たとえ引用がある場合でも著作権侵害となりますので注意が必要です。
画像・イラストの加工
著作権法は視覚芸術の作品も保護しています。これには、写真、イラスト、グラフィックデザインなどが含まれているので、許可なく他人の画像やイラストを加工することは著作権侵害です。
加工には、リサイズ、色調調整、合成、部分的なクロップなどが含まれます。たとえそれが微細な変更であっても、元の作品の著作権を尊重するためには、使用許可や適切なライセンスを得ることが重要です。
文章を丸々引用して一部を変更
他人の文章を丸ごと引用し、一部だけを変更したり加筆したりする行為も著作権侵害の可能性が高いでしょう。
著作権法は、オリジナルの表現形式を保護していますので、他人の文章を大幅に使用してその一部を変更するだけでは、その著作権を侵害する恐れがあります。
このような行為は、本来的な「引用」の範囲を超えており、著者の許可なしに行うべきではありません。
著作権侵害で発生するリスク
著作権を侵害した場合には、刑事罰が科されるケースもあるなど、思いがけず大きなリスクを負う可能性があるので注意が必要です。
損害賠償の請求
著作権侵害により、著作権者から損害賠償の請求を受ける可能性があります。これには、直接的な経済的損失(たとえば、著作権者が受けるべきだった利益)だけでなく、間接的な損失(評判の損失、イメージダウンなど)も含まれる場合があるでしょう。
損害賠償額は具体的な損失額や侵害の程度により、場合によっては非常に高額になることもあります。
刑事罰を科される危険性
著作権侵害は民法違反ではなく、犯罪として取り締まられる場合もあります。大規模な著作権侵害や営利目的の侵害の場合、罰金や懲役になるケースもあるでしょう。
これは特に、違法にコピーされたコンテンツを販売したり、無許可で大量に配布したりした場合に適用される可能性があります。
著作権を侵害された人は「差し止め」ができる
著作権侵害が行われた場合、著作権者は法的手段を用いて侵害行為の「差し止め」を求めることができます。これは、侵害行為を即時に停止させることを求める法的命令で、侵害行為が続いている場合や再発する可能性がある場合に適用可能です。差止命令が出された場合、それに違反すると、法的制裁を受ける可能性があります。
webサイト上で引用が示されておらず、著作権を侵害している場合には、サイトの閉鎖を求められるケースもあるので注意してください。
画像やSNSの引用はどうなる?
画像やSNSで引用を行うときは、それぞれ注意したいポイントが異なります。引用の仕方をしっかりと理解しておきましょう。
フリー素材は規約を確認する
“フリー”とはいえ、各画像素材サイトにはそれぞれの使用規約が存在します。商用利用や加工が許可されているか、引用の際にクレジット表記(著作権者の名前やソースを表示)が必要かどうかはサイトにより異なるのが実情です。
たとえば、一部のフリー素材は非商用での使用のみを許可している場合もあります。これらの規約を無視すると著作権侵害となる可能性があるため、素材を使用する前には必ず利用規約を確認し、遵守することが重要です。
SNSは埋め込み機能を活用する
SNSの投稿を引用する際は、各プラットフォームが提供している埋め込み機能を活用することを推奨します。
TwitterやInstagramなどでは、ユーザーが他人の投稿をウェブサイトやブログに埋め込むことを許可しており、これを利用することで正式な手続きでの投稿の引用が可能です。
埋め込みコードを使用すれば、自動的に投稿者のクレジットが表示され、著作権の問題を避けることができます。
ただし、この方法でも元の投稿者が投稿を削除した場合などには表示されなくなる可能性があるため、その点は留意が必要です。
Webメディアでは、記事の引用以外にも守るべきルールが存在します。以下の記事では、Webライティングでマスターしておきたいルールを解説しています。信頼されるWebライターになるために、ぜひチェックしておきましょう。
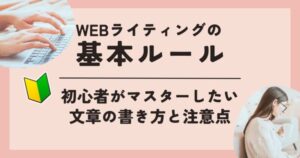
引用に関するよくある質問
引用する際に悩みがちなポイントは以下のとおりです。
引用できるかどうかで悩んだら、専門家に確認するか、引用しないで済ませられないかを検討しましょう。
スクリーンショットは引用しても問題ない?
スクリーンショットは他人の著作物を含む可能性があります。そのため、スクリーンショットの使用は引用の範疇である必要がありますし、それが可能な場合でも、引用元を明示し、必要な許可を取るなど、適切な手続きを経て行うことが必要です。
もし、スクリーンショットが他人の著作物を大量に、またはそのまま使用している場合、著作権侵害の可能性があります。疑わしい場合は法的なアドバイスを求めましょう。
著作権侵害が心配なときはどうすればよい?
著作権侵害を避けるためには、まず自分が引用しようとしているものが誰の著作物であるかを確認し、その著作権者から適切な許可を得ることが最も安全です。
公開されている作品であっても必ずしも自由に使用できるわけではなく、使用許可やライセンスが必要な場合があります。
疑わしい場合、または規模が大きい場合には、専門家の意見を求めることも考慮するとよいでしょう。
また、可能であれば著作権フリーの素材を使用する、オリジナルのコンテンツを作成する、などの選択肢もあります。
記事の引用まとめ
引用は他人の著作物を必要最小限に使用し、その使用が必要な状況下で、明確に区別して利用することを指します。
引用の基本ルールとしては、引用する必然性、引用箇所と自分の著作物の区別、自分の著作物が主体であること、そして出典の明示、といった要素があり、また、引用箇所を勝手に改変せず、オリジナルのソースから引用することも重要です。